2024.06.29
第33回ひょうご次世代育成塾を開講 小倉將信初代こども家庭庁担当大臣が講義 「少子化対策とこども家庭庁」をテーマに
6月29日の青年局・部合同大会終了後、午後3時から第33回ひょうご次世代育成塾が開講され、第52代党青年局長で初代こども家庭庁担当大臣を務めた小倉將信衆議院議員(東京23区)が、政府の異次元の少子化対策について、政策の意図するところ、目標値などを解説しました。

講義では、末松県連会長、黒川幹事長も傍聴する中、小倉氏は、「2030年代に入るまでの、6~7年が少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンス」と語り、出生数や出生率を目標値に掲げないのは「一人ひとりの人生に立ち入るべきでないとする考え方による。これはグローバルスタンダードである」と政策形成の基礎的な考えを説明するとともに「若い世代が希望通り結婚し、子どもを産み、育てることができる環境を整え、少子化トレンドを反転させる」と企図するところを説きました。
「重層的な取り組みがあってこそ効果」
また、「こども未来戦略方針」のポイントとして、30年代初頭までに3.6兆円を投資して、OECDトップのスウェーデンと肩を並べる水準になると規模を強調しました。
そのうえで「今年度から出産育児一時金の引き上げ・0~2歳の伴走型」、「来年度から児童手当を拡充、3人の子どもがいる家庭では総額で最大400万円増の1100万円に」、さらにその後の取り組みとして「高等教育の更なる支援拡充としての授業料減免拡大など」「出産育児一時金を42万円から50万円に引き上げるとともに26年度から出産費用の保険適用」などの取り組み内容を解説、スピード感を重視する視点を強調しました。


(写真左・政府の掲げる政策内容を解説する小倉將信衆院議員。写真右・出席者からは自治体との連携について質問が出ました)
このほか社会全体の構造や意識の変革が大事だとして、「男性の育児休暇取得率を30年までに85%に引き上げ,中小企業の負担増には助成措置を講じるなど配慮する」としました。
「子育てに冷たい国と海外からは見られているが、経済面だけでなく精神面でもバックアップできる意識改革が不可欠」「こども政策は国だけで出来るものではなく、めざす方向を確認する定期協議、意見交換の機会も必要」などと総括しながら、「目立ったことをひとつやればいいのではなく、重層的な取り組みが最も重要だ」と結びました。
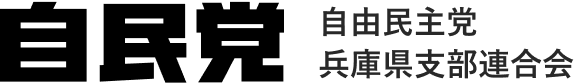

 選挙
選挙 議員
議員 実績
実績 政策
政策




